-
01
TOP
-
02
あなたのONE SCENE
鉢形駅
-
03
クロストーク
渡邉誠友さん
-
04
こよみ、くらし。
昭和レトロ
-
05
おとなの私のセルフケア
免疫力の話
-
06
ちょっと、そこまで
船橋編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説「てむちゃん」
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
上州絹タオル
-
11
「パズル」でアタマの体操
クロスワード
-
12
バックナンバー
-
13
最新号
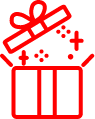 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!

プロフィール
日光下駄 みやび
| わたなべ・せいゆう | |
| 渡邉 誠友 | さん |
1983年生まれ、栃木県宇都宮市出身。2014年4月に日光下駄職人の元に弟子入りし、2022年4月に独立。東武宇都宮百貨店や日本橋三越本店などに出店するなど、各地で活躍中。
職人の技が光る、日光下駄という栃木県の伝統工芸品をご存じでしょうか?
江戸時代に日光の社寺を参拝する際、砂利や雪で覆われた境内を歩くために生まれた独特の形状をした歴史ある履物です。
宇都宮にある工房兼ショップを訪ねました。
江戸時代からの伝統を次に継承する―
そんな思いから新たなことにも挑戦
軽い気持ちで始めた
単純な、でも難しい手仕事

――日光下駄の職人になられたきっかけは?
正直にお話ししますと、実は私の母がきっかけなのです。母が和服を着る際の履物を探しているときに、私の師匠となる日光下駄の職人さんに出会いました。そこで職人さんから「日光下駄の世界は後継者不足で困っていて……」という話を聞き、母は「私の息子でよければ、顔合わせをしませんか?」と言ったのです。
そのころの私は、とくにやりたい仕事があったわけでもなく、ただ何となくサラリーマンをしていました。子どものときから絵を描いたり、何かを作ることが好きでしたので、ひとまずお話を伺うことにしました。すると、おもしろそうな世界だと興味が湧き、弟子入りすることに。でも、正直なところ、向かなかったらやめても……ぐらいの軽い気持ちでした。
――弟子時代はどんな仕事を?
草履の編み方など、ひと通りの工程を最初に教わりましたが、私の師匠の教えは、とにかく実践あるのみ。最初の1年間は、販売する商品ではなく、ひたすら草履を作ることを反復していました。2年目あたりから少しずつ、販売できる状態のものができるようになりました。
日光下駄を作る工程は、竹の皮を細くしたものを編んでいく、単純な作業といえます。でも、単純だからこそ難しい。見た目もそうですが、履き心地にもつながりますので、いかに細かく美しく編めるかがたいせつなのです。
こうした細かい作業は根気が必要ですが、私には向いていたようで、今でも苦に感じることはありませんね。
――日光下駄とはどんな履物か、教えていただけますか?
麻を紐状に縒り、それを草履の形にして、その間に細く切った竹の皮を編んでいくと草履ができあがります。軽さが特徴の桐の台木に、この草履を栃木県内の鹿沼の特産品である野州麻の紐で縫い付けて完成します。ひとつの日光下駄を作り上げるのに、おおむね2日間かかります。
この履物が生まれたのは、江戸時代にさかのぼります。徳川家康公が祀られている日光東照宮をはじめとした日光の社寺では、境内に参入する際の作法や服装に格式を重んじた決まり事がありました。表門で清めの草履に履き替えるのも作法のひとつ。しかし、境内は砂利道が多く、冬は雪も積もるため、高さのある下駄の上に草履をのせたものが考案されたのです。これは、御免下駄と呼ばれていました。その後、明治時代になり、より実用的に改良が加えられ、日光下駄が誕生しました。

縦と外側を麻紐で組み、竹の皮を隙間なくしっかりと横に編んでいく草履作りの工程
新しいセンスで
独自のアイテムも誕生
――オリジナルの草履サンダルとは、どういった履物でしょうか?
日光下駄の桐の台木を特殊なスポンジに変えたものが、私が生み出した草履サンダルです。底面はやわらかいですが強度もあり、軽くて気軽に履けるので、屋外でも室内でも使っていただけるのが魅力です。訪問着等の着物では格式が下がってしまうため、フォーマルな着物にも合わせられる草履仕様の商品も考案しました。
私は、県内におそらく5人いる日光下駄の職人のなかで最年少です。現代の生活に合わせた新しい感覚の商品を生み出し、多くの人に履いてもらえれば、次の世代に日光下駄が継承されていくのだと考えています。カラフルな商品も生み出したことで、和装の方だけではなく、洋服に合わせる若い方も増えました。

竹の皮の産地を訪ねた
八女の旅が思い出に
――日光下駄作りに生かされた、印象深いご旅行はありますか?
草履に用いるこの竹の皮は、暖かい限られた場所にしか生えない、特殊な竹のもの。一般的な竹の皮にある黒い斑点が少ない白さが特徴で、皮か白しろ竹だけと呼ばれる幻の材料なのです。最上級のものは、斑点ひとつない美しさです。
近年はだいぶ採れなくなってきていると聞き、国内唯一の産地である福岡県の八や女めを旅したことがありました。収穫は梅雨の時期がメインなのですが、皮がぬかるんだ地面に触れ続けると腐敗して、使いものにならなくなってしまいます。そして、ひとつひとつを手作業で収穫するたいへんさも知りました。やはり現場を見ると心持ちが変わるもので、上質な皮が非常に貴重であることを痛感。これまでよりもありがたく使わなければいけないと感じ、今もその思いを持ちながら作業をしています。
八女は、日光東照宮の材料となった素材も運ばれた話も伝わり、日光とつながりがあったようです。日光下駄もこうしたゆかりがあって、誕生したのかもしれませんね。
――リラックスするなど、お気に入りのおでかけ先はありますか?
同じ栃木県内の那須が好きで、暖かいシーズンに妻とよく訪れています。日頃は細かな作業を淡々と行っていますので、緑豊かな自然に囲まれて、車通りも少ない静かな環境は、落ち着けます。人の温もりを感じるペンションに泊まれることも魅力に感じています。
インフォメーション
渡邉さんの工房&ショップはこちら


日光下駄 みやびにっこうげた みやび
夏は涼しく、冬は暖かい日光下駄のほか、オリジナルの草履サンダルなどが並ぶ店内。鼻緒や草履表の色、下駄台の色などを選んで、オーダーメイドすることもできます。そのほか、県内作家の和雑貨なども販売。
- 028-623-1470
- 栃木県宇都宮市今泉町448-1
- 13:00〜18:00
- 水・日曜、その他臨時休あり
- 東武宇都宮線 東武宇都宮駅から白沢河原行きバス、今泉八丁目下車すぐ
text : Taku Tanji photo : Chiemi Shimizu



