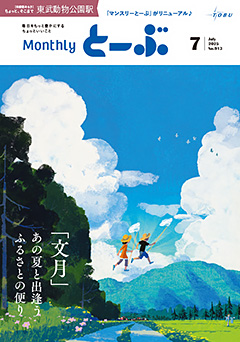-
01
TOP
-
02
あなたのONE SCENE
大堀川水辺公園
-
03
クロストーク
朝霧重治さん
-
04
こよみ、くらし。
七夕
-
05
おとなの私のセルフケア
熱帯夜が快適になった話
-
06
ちょっと、そこまで
東武動物公園編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説「てむちゃん」
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
干しそば
-
11
「パズル」でアタマの体操
クロスワード編
-
12
バックナンバー
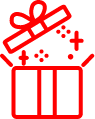 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!

プロフィール
株式会社協同商事(COEDO BREWERY)
| あさぎり・しげはる | |
| 朝霧 重治 | さん |
1997年に一橋大学を卒業後、三菱重工へ入社。その後、義父が経営する協同商事へ入社し、2003年に副社長、2009年に代表取締役に就任。農業や地元・川越へ熱い思いを抱き、精力的に活動中。
クラフトビール「COEDO」を醸造しスペーシア Ⅹ車内で提供中の「Cedar X PA」も手がけた、川越を拠点とする協同商事。
どのような思いから「COEDO」が生まれ、どういった将来像を描いているのか――。
社長の朝霧さんにお話を聞きました。
サステナブルな日本の農業と
共存するクラフトビールをめざして
農業を原点として
ビール造りがスタート
――ビール造りを始めた経緯は?
私の義父が設立した私たちの会社は、農産物を生産する川越の方々と結びつき、産直という活動を始めたことが起源となっています。その後、漢字で表記していた「小江戸ビール」が誕生しました。
農業とは「業」という文字が付くことからもお分かりのとおり、「インダストリー」です。古くからこの地では、土壌を健全に保つために緑肥(緑の肥料)として麦を植え、土に漉すき込む農法が取り入れられていました。この麦を収穫しても収益は上がりませんが、付加価値を付けられれば農業の未来が明るくなるのでは――。これがビール造りの着想です。
さらに、地のものを使ったビール造りを模索して注目したのが、形や大きさが規格外として廃棄されていた、川越特産のサツマイモ。サツマイモラガーである今の「紅赤-Beniaka-」につながる商品が生まれました。
こうしたビール造りが評価され、2008 年に農業と商業と工業が連携した取り組み「農商工連携の88選」の1番目の事例に選ばれました。

埼玉・東松山にある麦の自社農園。秋に種をまき、5~6月に収穫期を迎えると、一帯は目を奪われるような黄金色に染まります
――2006年にブランド名をアルファベット表記に変えた理由は?
観光地のみやげ物としての地ビールではなく、クラフトビールという概念を皆様に提案するためです。地ビールブームが去った後、独自性のあるビール造りが求められ、私たちのビールの魅力をきちんと、改めてお伝えすることがいちばんの狙いでした。
私は経営する立場として、サステナブルな考えを大切にしています。もっと環境への負荷を減らし、無駄を減らしたビール造りをめざした取り組みも行っています。ビール醸造の過程で廃棄対象のもみ殻はすべて、肉牛・乳牛の飼料となっています。排水は、有機物を含む排水を有機物を使ってメタン発酵させる技術を活用していまして、その排水処理施設を増強するタイミングがちょうど今、訪れています。メタンガスは発電に使用しています。
料理とビールを合わせて
食中酒として楽しんで
――COEDOビールのおすすめの楽しみ方を教えてください。
缶やボトルそのままではなく、まず透明なグラスに注いでみてください。いろいろな色合いのビールがあり、まずは目で楽しめます。さらにグラスを口に近づける飲み方の方が香りがより広がります。
食中酒として料理と合わせるなら、ビールの色と食材の色がシンクロした料理がおすすめです。茶褐色のビールには豚肉や鶏肉、濃い色合いのビールには牛肉、サツマイモを使ったビールには、焼き鳥やうなぎのかば焼きなど、カラメル化した甘みのあるソースの料理がよく合います。

サステナブルな日本の農業と共存するクラフトビールをめざしてホップが香るセッションIPAの毬花-Marihana-(左)やピルスナーの瑠璃-Ruri-(中央)、サツマイモを使った紅赤-Beniaka-(右)
サステナブルな農業と
ビール造りの未来へ
――新たな取り組みの内容は?
現在は移転する準備中でクローズ(2025年秋、新店オープン予定)していますが、2022年1月にオーガニック野菜の量り売りのお店を埼玉の大宮に開店しました。少しでも地球環境に配慮した持続可能な農業が求められる今、その答えが有機農法であると知ってもらうのが八百屋の目的です。
一般的な野菜のように袋詰めすることもやめて、量り売り、つまりかつての八百屋さんのスタイルの方が理にかなっているとも考えました。
さらに、私たちの有機農法への決意を見せるために、埼玉・東松山のある土地にたい肥を入れて3年間をかけて土を改良し、有機の麦畑を作りました。ビール造りを始めた当初、緑肥として注目した麦とようやく、きちんと向き合えるようになったのです。

国内外での経験が
自分の引き出しを広げる
――「おでかけ」という言葉に感じることは?
趣味は何ですかと聞かれれば、「旅」と答えるほどおでかけすることが好きです。仕事で各地を訪れる際も、現地の風土をできるだけ体験することを心がけています。
学生時代はバックパッカーとして世界各地を旅しましたが、今思い返せば、この経験がビール造りに生かされている気もします。ロンドンのパブでは多くの種類があるのに、ただビールをくださいとしか言えず、ミュンヘンではこんなにもビールの味が違うのだと驚きました。ビールの世界が広いことを知ったのです。
視点を広げてくれるという意味で、旅とビジネスはつながっているのだと感じています。自分の引き出しが広がっている――、そんな感覚でしょうか。
――東武鉄道にまつわる思い出は?
私の幼少期、川越駅が木舎だった記憶が鮮明に残っています。東上線の車内の床も木でした。このように、東武鉄道は私にとって、生活とともにある存在です。
WEB限定!
朝霧さんが抱く
農業や川越への思い

――農業への関心が高まったのはなぜでしょうか?
私は川越の農村で育ち、実家の周辺には畑が広がっていました。私にとって農業は、遠くの誰かが行っているものではなく、身近なものであり、農村は私の原風景なのです。協同商事が取り組んでいた農業と関わる仕事は、異次元の世界に飛び込むのではなく、自然な流れのような感覚です。
川越といえば蔵の町を思い浮かべる方が多いかと思いますが、あの一帯は川越藩の時代から続く商業の街で、周辺は農業地帯でした。この地域は、武蔵野台地の北端に位置しています。台地という場所は、米作りに向いていませんので、畑が作られました。野原だったために武蔵野という地名が付けられたといわれていて、火山灰土が積もったあまり豊かではない土地だったのです。
70×700mの短冊状の土地を藩から割り当てられ、道を整備して、村を造り上げました。道を挟んで人家と畑が向かい合い、冬の北風を防ぐために道沿いに防風林を植えました。その木々は杉や檜ではなく広葉樹だったため、落ち葉を集めてたい肥を作る農法が生まれたのです。
加えて、江戸時代はリサイクルが進んだ時代でしたので、都市部で発生した人糞なども村に運ばれてきて、発酵させて肥(こや)しになりました。世界的に見れば、豊かな土地を求めて移り住んでいくことが人類の歴史とも言えますが、自分たちの土地をあきらめず、みずからの力で何とか豊かな土地をつくり、今でいう循環型社会をつくり上げた日本人――。先代からこうした話を聞き、すごいことを成し遂げたのだと感じました。
――地元・川越との関わりは?
2020年、私たちのビールと中華をベースにした料理が楽しめるレストランを川越駅前にオープンしました。蔵造りの街並みが続き、観光客が集まる川越一番街では、多くのお店で私たちのビールを販売していただいています。その場所にお店を構えては、地元のお店と競合することになります。私たちは、郊外でものをつくり、市中で酒屋さんなどで売っていただくのがあるべき姿です。
さらに、駅周辺はあまり外食産業が盛んではなく、とはいえ地元の人は観光客で混雑している一番街へは足を運びません。そんな外食難民とも呼べる地元の人々が、気軽に訪れてもらえるお店にもしたかったのです。
また、川越観光協会や地元ブランドの向上をめざす川越ブランディング委員会、さらに埼玉県物産観光協会などにボランティアで参加しておりまして、地元の人々と一緒によりよい状態にしていく取り組みを行っています。
インフォメーション
COEDO BREWERY THE RESTAURANT
コエドブルワリー ザ レストラン
COEDOビールの樽生が味わえる直営店はこちら
自社製のクラフトビールや中華をベースにしたフードメニューがそろったレストラン。テイクアウト専門のCOEDO KIOSKも併設しています。

- 049-265-7857
- 埼玉県川越市脇田本町8-1
- 平日11:30~15:30(L.O.15:00)、17:00~22:00(L.O.21:00)。土・日曜、祝日は11:30~22:00(L.O.21:00、15:00~16:00はドリンクのみ)
- 無休
- 東上線川越駅から徒歩3分
text : Taku Tanji photo : Kota Yamashita