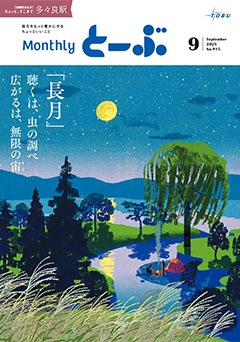-
01
TOP
-
02
あなたのONE SCENE
晴雲酒造
-
03
クロストーク
京山幸枝若さん
-
04
こよみ、くらし。
防災
-
05
おとなの私のセルフケア
365日湯船が欠かせない話
-
06
ちょっと、そこまで
多々良編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説「てむちゃん」
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
お芋のバスクチーズケーキ
-
11
「パズル」でアタマの体操
スリザーリンク編
-
12
バックナンバー
-
13
最新号
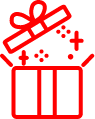 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!

プロフィール
浪曲師・人間国宝
| きょうやま・こうしわか | |
| 京山 幸枝若 | さん |
1954年生まれ、兵庫県姫路市出身。17歳で実父でもある初代・京山幸枝若に入門し、2004年、二代目京山幸枝若を襲名。文化庁芸術祭大衆芸能部門大賞や芸術選奨文部科学大臣賞などを受賞後、2024年に重要無形文化財(人間国宝)に認定。
落語や講談と並ぶ日本の三大話芸のひとつ「浪曲(ろうきょく)」。歌と語りで物語を演じる浪曲は、いわば日本のミュージカル。
二代目・京山幸枝若さんは、この伝統芸能の技が高く評価され、昨年、浪曲師初の人間国宝に認定されました。
ここでは浪曲の魅力や未来について語っていただきました。
最高峰の技で浪曲の人気を復活させ
伝統的な大衆芸能の魅力を若い世代へ
幼い頃に別れた実父
初代・京山幸枝若へ弟子入り
――浪曲初心者の方々へ、浪曲という話芸の楽しみ方を教えてください
浪曲は曲師(きょくし)が弾く三味線に合わせて歌っていく節(ふし)と呼ばれる地の部分(筋や状況説明の箇所)と、啖呵(たんか)と呼ばれる会話(台詞(せりふ))の部分で成り立っています。ネタにはいろいろなジャンルがあるので、初めて聴く方は自分の興味があるジャンルのネタを選んで聴くといいと思いますね。お笑いが好きなら笑えるネタ、お涙ちょうだいが好きなら人情ものや悲恋もの。ほかにも清水次郎長伝(しみずのじろちょうでん)なんかの侠客(きょうかく)ものや、忠臣蔵やらの武家ものなんかもあります。
浪曲師の中ではそれぞれのジャンルを専門でやっている人が多いですが、私の場合はいろんなジャンルのネタをやります。いろいろできた方が得やからね(笑)。だからその場でネタを変えることもあります。「今日はどんなお客さんかな」と探りながら始めて、例えば初めの口上で「今日の客は笑わへんな」と思ったら、すぐ人情もんの親孝行の話とかに変えるんです。すると涙流して聴いてくれるんですよ。

――浪曲との最初の出合いは?
学生時代に友人が「これ聴け」ってLPレコードを持って来たんです。それが歌謡浪曲で、私が「これ浪曲やないかい。浪曲ゆうたら(だみ声で)〽旅ゆけば~っていうやつやろ」と言うと、「お前、古いなー。浪曲といえば幸枝若や」言われました。そのレコードが初代京山幸枝若の『瞼(まぶた)の母』だったんですよ。当時私は趣味でギターを弾いて、フォークソングや歌謡曲を歌ってたんですが、そのレコードを借りて1週間で覚えたんですよ。すると友人に「お前、天才やな。幸枝若の弟子になれるど」と言われました(笑)
――浪曲を始められたきっかけは?
育ての父が興行師で、その頃は漫才大会やら歌謡ショーやら刑務所の慰問やらであちこち回ってましてね。ちょうどその時期、私は病気の後で、体が回復して家でうろうろしてたんです。すると父から「お前もなんかやれ」言われて。それで、母の三味線に合わせてギターと歌をやっていたんです。
そしたら今度は父から「浪曲が売りの温泉の舞台に出るから、浪曲を覚えろ」と言われたので、立川談志師匠が司会の『浪曲特選』という番組を見つけて録音したんです。それが初代京山幸枝若の相撲ネタの『雷電と八角』でした。それを覚えて温泉の興行でやったんが最初ですわ。

写真:宮岡里英
リズミカルで聞きやすい、初代の幸枝若節を継承。多彩なジャンルのネタができるのも幸枝若さんの魅力(曲師:虹友美)
――初代・幸枝若師匠に弟子入りされたきっかけは?
弟子入り前から、姫路の敬老会とか農協なんかの仕事で、休みなしでずーっと浪曲をやってたんですが、この頃からよく周りの人たちに「幸枝若そっくりやな」言われてまして。そしたらある日、芸人さんに「幸枝若さんが喜んでたで」言われて。それでお袋に「お母ちゃん、俺、幸枝若の子か?」って聞いたら「そやで」と返されました。それで納得しました。「そうか、だから俺、すぐに浪曲できたんや」って(笑)。やっぱりDNAは怖いですよね。
それから幸枝若が出る浪曲大会の仕事も入るようになって。そしたらうちのお袋に「お前な、幸枝若の節とネタを使ってるから、弟子にしてもらいに行こ」言われて、それで弟子になったんです。
幸枝若さんの好物は塩昆布と納豆!?
――〝食〟の思い出についてお聞かせください
仕事先ではおいしい食事を出していただきますが、ごちそうも毎日続くと、だいたい3日目頃から食えなくなるんですわ。だから大阪から塩昆布持ってってね、それを茶漬けで食べるんですよ。「うまいわ~」言うてね(笑)。
子どもの頃の思い出は、当時一番食べたかったものがありました。育ての父がね、朝から酒を飲みはるんですよ、納豆をつまみに。納豆を2粒ほど食うては酒を飲むんです。それを私が「うまそやなー」思て、学校行かんとジーッとご飯茶わんを持って、納豆をにらみつけるんですよ。するとお父さんが5粒くらいくれるんです。それをガーッて食べて「うわー、こんなうまい食いもんが世の中にあるんかー」って。大人になったら腹いっぱい食べたろ思いましたね(笑)。
人間国宝として思う
浪曲の未来と浪曲師の育成
――浪曲界の将来や、今後の目標についてお聞かせください
まずは若い人材の育成ですね。どんどん若い子を増やして、一人でも多く世に出すのが自分の目標です。せっかく浪曲師として重要無形文化財の認定を受けたわけですから、今がチャンスなんです。現在、浪曲師は全国で50~60人ぐらい。全盛期の頃は3000人もいたんです。
これからは若い子らにいろんなことをやらしてね。グループやらコンビやら、3人で掛け合いやったり、コントやったり。かっこええ子や、かわいい子を集めたりしてね。それでその中に浪曲を盛り込むんです。世の中に「浪曲はおもしろいな~」って言わせて、そんな中で若い浪曲のスターが出てくれたらと思いますね。それが自分に課された使命だと考えています。

WEB限定!
――プライベートではあまり外出されないと伺いましたが、普段外食には行かれますか?
最近は友達同士で、大阪のミナミにメシ食いに行くぐらいですかね。普段は仕事先で食事を出していただくことが多いので。
昔は大阪の十三(じゅうそう)にあったカウンターだけのカレー屋へ、よくチキンカレーを食べに行きました。
それから巡業していた頃、お弁当が出えへんときには、よく主催者から「これで食べてください」と1000円いただいて食事に行ってましたね。当時、市民会館とかのレストランだとカレーライスが700円か800円くらい。私はカレーが好きやから毎日カレーを食べに行ってました。
その頃、泉ピン子さんのお父さんで、浪曲師の江口鉱三郎さんが所属していたプロダクションがあって、そこの専務さんに可愛がってもろてたんですが、その専務もカレー好きでね。ほんでレストラン行ったらいつも会うんですよ。「またカレーかい」ってね(笑)。
――今まで最も印象的だった口演は?
二十歳ぐらいの頃やったかな、まだ幸枝若でなく福太郎だった頃。淡路島に福良いうところがあって、そこの公民館みたいなところで『清水次郎長伝』の『吉良の仁吉(きらのにきち)』というネタをやったんです。
仁吉の兄弟分の長吉(ながきち)が、穴太徳次郎(あのうのとくじろう)に縄張りの山を取られ、それを取り返えすために徳次郎とひと喧嘩しよう思て、仁吉に助太刀(すけだち)を頼むんです。
せやけど、仁吉の妻のお菊は徳次郎の妹や。長吉は仁吉に頼むんは筋が違いやと帰ろうとする。すると仁吉は長吉の助太刀のために、涙ながらにお菊に離縁状を渡すんです。お菊が「いややー」言うても、涙流して別れるんです。それで喧嘩の最後には次郎長一家も乗り込んできて、みんなで長吉の助太刀をして勝利します。
この場面を浪曲でやったんです。でもね、ネタが終わっても拍手がないんですよ。最後に緞帳(どんちょう)が下りても拍手がない。あれ? ウケてないのか?……と思てたら、突然「どわーっ」と拍手が起こって。
そんで客席の4、5人のおばちゃんがバーッと立ち上がって「付いて行く〜」言い出して(笑)。仁吉が兄弟分のために、離縁してまで助太刀するっていうのがかっこよかったんやろね。
そのあとすぐ主催者が楽屋へ来て「ぜひもう一席お願いします!」言うたんです。でもほかの皆さんもいてはるんで、すぐにもう一席というわけにもいかず「また今度改めて呼んでください」言うたんですね。
ところが客席では「福太郎出せー」「帰すなー」と大騒ぎで(笑)。だから公民館を出る時は、軽トラの後ろに寝かされて、上からむしろをかぶされて帰ったんです(笑)。
あんな、緞帳が下りてから「どわーっ」「おぉーっ」と拍手が来るのは初めてでしたわ。お客さんもネタに入り込んで、やってる本人もその役柄に入り込んでしもうて。うちのお袋も「今日はようできとったな」言うてました。とにかく、そこまでウケたことはないわ。
54年間浪曲やってますが、ほんまにそれは一番思い出に残ってますね。
インフォメーション
2025年11月1日(土)
第27回 京山幸枝若 独演会
人間国宝の語りと節を生で楽しんでみませんか

写真:宮岡里英
- 会場 浅草木馬亭 浅草駅から徒歩約7 分
- 開演 8:00(開場17:30)〜20:00
- 全席自由 前売り4000円、当日4500円
お問い合わせ・予約はこちら
- 046-876-9227
- メール:hana-ni-awan@oct.email.ne.jp
SMS:080-3206-6601
text : Takako Inamoto photo : Chiemi Shimizu