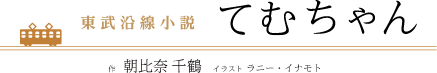-
01
TOP
-
02
あなたのONE SCENE
新河岸駅~川越駅
-
03
クロストーク
春風亭一之輔さん
-
04
こよみ、くらし。
すす払い
-
05
おとなの私のセルフケア
3分間の魔法の話
-
06
ちょっと、そこまで
鐘ケ淵編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説「てむちゃん」
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
MIYA バターサンド
-
11
「パズル」でアタマの体操
スリザーリンク編
-
12
バックナンバー
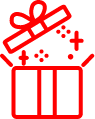 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!
第12話年の瀬のひとときを

「よっ!」
威勢のいい掛け声の後、手拍子が続く。
パパパンパパパンパパパンパッ!
年末、市役所前の広場で開かれる羽子板市は、払田家にとって一年の締めくくりの大切な行事だ。羽子板を購入した若夫婦と赤ちゃんには、周囲から拍手が贈られる。私は、その瞬間が好きだ。掛け声役のパパは、法被姿でここぞとばかりに声を張る。
「この役は、お婿さんが来てもずっとやりたいなあ」
「お婿さん? 誰の?」
父の言葉についトゲのある返事をする、私、払田瑠璃。先月に31歳の誕生日を迎えたため、そろそろ人生設計を考え始めなければと焦っていた。
ふと、同い年の義妹、てむちゃんが遠巻きに様子をうかがっているのに気づいた。
「てむちゃん、他人のふりしないの。みんな羽子板屋の娘って知ってるんだから。ほら、法被着て呼び込みして」
「瑠璃、声かけないで。サクラなの、私」
昨年末までアイドル仕事をしていたてむちゃんは、今年初めて羽子板市に立つので勝手がわからないようだ。
「稲子! ここで笑顔で立ってなさい!」
ママが大きな声でてむちゃんを呼ぶものだから、渋々てむちゃんは店に戻ってきた。
「わー、てむちゃん、一緒に写真撮ってー」
小学生高学年くらいの子がやってきててむちゃんに話しかけてきた。とっさの表情管理は、アイドル時代から完璧だ。
「あの営業スマイルは、修業の賜物だな」
パパが私にこそりと呟いた。
「そうだね、口角めっちゃ上がってる」
「そうはいっても、辞めたからなあ。稲子もそうだけど、瑠璃もどうするんだ」
「どうするって?」
「3月で仕事の契約、切れるんだろ?」
考えたくない現実を指摘されると答えに詰まる。
「……更新してもらうつもり」
言いながら、自分でも声が小さくなっていくのがわかった。
「瑠璃はやりたいことないのか? 結婚も向いてると思うぞ?」
「婿とか結婚とかそういうプレッシャー、今や家族でもNGだよ」
「そういう選択肢もあるって言ってるだけなのになあ」
パパはたまに、昭和時代にタイムスリップする。今は幸せの価値観は人それぞれ。親にも決められない。
とはいえ、てむちゃんは一番やりたかったアイドルを年齢で強制終了させられ、この1年間ふわふわと漂う雲のように過ごしてきた。幸せにも終わりはあるのを、身をもって知ったはずだ。私も来年そうなる?いや、私はそもそも、やりたいことなんてない。誰かの役に立ちたいと思って過ごしていたら時間が経っていた、それだけ。でも誰かって誰だったっけ……。
おめでたい手拍子と裏腹に、心が沈んでいった。すると、お客さんが話しかけてきた。手には、しめ飾りを持っている。
「これ、いくらですか?」
庭の南天とカラスウリの実を組み合わせて作ったしめ飾りは、私の初めての作品だ。
「あ、ありがとうございます!」
お客さんに商品を渡した途端にパパが「よおっ」と威勢のいい声をあげ、手拍子をした。お客さんの喜んでいる様子がこちらにまで伝わってきた。嬉しい!
「来年からジャムも一緒に売ったら? 食品関係の免許を取ればいいじゃない?」
ママが嬉しそうに言った。
「そうだよ。瑠璃は好きなことがいっぱいあるんだから。日々楽しそうで羨ましい」
驚いた。ずっと好きを突き詰めてきたてむちゃんにそんなことを言われるなんて。
「好きなことがあるからって、やりたいことがあるってわけじゃないよ」
そう返すと、てむちゃんは首を傾げた。
「やりたいことって、好きから始まるんじゃないの?」
何気ない言葉が矢のように胸に刺さった。好きから始まるやりたいこと? ジャムやお飾り、リースなど、家の周りのものを使って何かを作ることは好きだ。それをやりたいことにして生きていく……?
「瑠璃の作る季節のジャム、毎回隠し味変えたりしてて楽しんで作ってるの、わかるよ」
「え? そう……かな?」
目の前に薄がかっていた霧が引いていき、急に視界が開けた気がした。すると、てむちゃんが手を叩いた。
パパパンパパパンパパパンパッ!
澄み渡るような冬の青空に響く手拍子は、何かとても縁起のよいもののように思えた。
来年はきっといい年になる。
そうしようね、てむちゃん。
プロフィール
文筆家、脚本家。2021年日本シナリオ作家協会主催「新人シナリオコンクール」佳作受賞。現在は、小説執筆のほか、脚本家としてテレビや映画の仕事に携わる。