-
01
最新号
-
02
あなたのONE SCENE
ひばり
-
03
クロストーク
辻直人さん
-
04
こよみ、くらし。
節分
-
05
それはさておき、コーヒーでも。
だから冬には熱々のココアが必要だ
-
06
ちょっと、そこまで
相老(あいおい)編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説
てむちゃん on the way
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
レアチーズケーキや焼き菓子
-
11
謎解き教室
-
12
バックナンバー
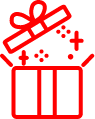 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!
第14話厳冬に訪れる場所

「トラはライオンとは違って、2歳で親から自立して群れをつくらずに生きるんです。みんな、聞いてる!?」
近所の東武動物公園にホワイトタイガーのリュウがやってきた当時、私は小学生だった。いち早く地元のみんなに見せたいと張り切って課外授業に連れてきてくれた先生の説明は、皆、物珍しい動物に夢中で聞いていなかったように思う。
か、かっこいい!
私は、まるでヒマラヤの雪神のようなリュウの気高い佇まいに心を奪われ、しばらく動くことができなかった。希少な動物で、群れずに孤独に生きるという説明も、何か印象に残った。
今冬の最低気温を更新した朝、私は嬉々として動物園にやってきた。予想通り、開園すぐの園内は閑散としている。こんな日はゆっくりと神殿づくりのホワイトタイガー舎前を陣取るに限る。
檻の中には気持ちよさそうに毛繕いしあうコタとハクの兄弟トラがいた。それはそれで勇猛な動物というよりも、大きな猫のようで可愛らしい。
「ねえ、いつまでそこにいるの?」
突然、背後から女性の声がした。振り返ると、巨大なバズーカ砲のようなレンズが私を狙っていた。
「えっ、わっ!」
驚いて横に退いた途端、バシャバシャバシャ!と凄まじい連写音が鳴り響いた。
なんだ撮影したかったのか。それにしても大きな望遠レンズだ。こんな近いのに、そのレンズ必要? 私はその気配がわかるくらいにじーっと彼女を見つめた。けれども女性は全く意に介さず、夢中で檻の中を撮影している。この光景、見たことあるなと思ったら、そうだアイドルの撮影会だ。
「あのー」
呼びかけるが、反応はない。しばらく彼女を背後から眺めることにした。彼女もまた、珍しい動物のようで、見ていて面白かったのもある。
コタが奥に引っ込んだタイミングで、彼女は急に振り返った。
「何」
あ、聞こえてたんだ。ベレー帽を被った女性はかつて自分を撮影してくれていたファンと同じように、多くのポケットがついたベストを着用していた。カメラを下ろした彼女は、意外にも若々しい。もしかしたら同年代かもしれない。
「熱心ですね。コタかハク、どちらかのファンなんですか?」
つい、そんな質問をしてしまった。
「……そうじゃなきゃ撮らないでしょ」
「推し活だ」
「……まあ、そうとも言えるかも」
「へえ、何かに発表してるんですか?」
「……別に」
ものすごく愛想が悪い。ここまで取り付く島がない人も珍しい。普段ならすぐに離れるタイプだ。でも、極寒の中、他に誰もいない動物園で、同じタイミングでホワイトタイガーに向き合っている。物好き同士の奇妙な連帯感が、私をこの場に留まらせた。
「ホワイトタイガーのどこが好きなんですか?」
「……孤高の姿が、かっこいいでしょう」
彼女は、昔の私が抱いた印象と同じように彼らを見ていた。
「でも、この子たちは戯れあってて、そうでもないですよね。可愛いけど」
「……カーラは、そうだったから」
「カーラ、ああ、死んじゃいましたよね」
「……」
彼女は無言でカメラを構えた。何かまずいことでも言ったかなと思ったが、撮影目的のときは、空気を読むよりも撮影の瞬間が最優先。今がシャッターチャンスなのかもしれないと黙った。そして、彼女の撮影姿を1枚だけ撮ってその場を離れた。
後日、SNS にホワイトタイガー舎前に立つ、自分の後ろ姿の画像が送られてきた。私がコタとハクを撮影し、タグ付けしていたのであの時の人だとわかったようだ。
ByakkoC3という彼女のアカウントは、さながらカーラの写真集だ。透き通るような碧い瞳とその慈愛に満ちた眼差し、凛とした横顔……さまざまな瞬間が愛おしい。最新の写真には、「ありがとう。あなたのおかげで家から出ることができました。あなたは恩人です」とコメントが添えられていた。そこには、彼女がカーラと共有した大切な時間があった。
送られてきた画像には、何の言葉も添えられてなかった。私もまた、彼女を撮影した1枚をそのままに送った。
私たちが共有した、この冬の記憶。
プロフィール
文筆家、脚本家。2021年日本シナリオ作家協会主催「新人シナリオコンクール」佳作受賞。現在は、小説執筆のほか、脚本家としてテレビや映画の仕事に携わる。



