-
01
TOP
-
02
あなたのONE SCENE
新鎌ケ谷駅
-
03
クロストーク
荒井詩万さん
-
04
こよみ、くらし。
文化の日
-
05
おとなの私のセルフケア
アンバランスさに気づかされた話
-
06
ちょっと、そこまで
朝霞編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説「てむちゃん」
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
清酒・分福、於波良岐など
-
11
「パズル」でアタマの体操
数独編
-
12
バックナンバー
-
13
最新号
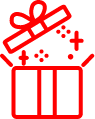 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!

プロフィール
インテリアコーディネーター
| あらい・しま | |
| 荒井 詩万 | さん |
日本女子大学家政学部卒。住宅やマンションのコーディネート、リノベーションを数多く手掛け、住まう人に寄り添う心地よい空間づくりが人気。講師やTVをはじめとしたメディア出演など幅広く活躍しています。
師走をひと月後に控えたこの季節。
大掃除の際に模様替えをしたいな……と
考えている方がいらっしゃるかもしれません。
今号は、マルチに活躍する荒井 詩万さんのご自宅を訪ね、
自宅をすてきな空間へと生まれ変わらせる
いろいろなヒントを聞いてみました。
〝余白〟のある空間づくりが
美しい暮らしにつながります
その後の変化に対応できる
余白のある空間づくりを
――すてきな空間のご自宅には、どのようなアイデアが?
自宅のコンセプトは「ギャラリーに住まう」です。私たち夫婦の共通の趣味が美術館やギャラリーに足を運ぶことでして、そこで購入したさまざまな小物などを飾れるスペースがある空間を考えました。
もうひとつは、フレキシブルに使える空間であること。たとえば、壁側のソファと奥側のピアノの間にスペースを設け、ちょっとしたピアノの演奏会を開いたときは椅子を並べられるなど、自由に使えるようにしました。中庭に面した窓も大きくし、天井にも自然光が入る窓、階段の奥にも細長い採光部を設けて明るく開放感のある空間もめざしました。
さらに、余白のある空間ということも大切にしています。お話ししたソファ前のスペースも余白のひとつ。さまざまな物をぎゅうぎゅうに詰め込み過ぎてしまうと、ライフスタイルの変化など変わっていくさまざまなことに対応できません。たとえば、気分によって飾っていた絵が変わるかもしれない、クッションも変わるかもしれない……。そのときに変えていけるような余白をつくりました。

――コーディネートをする際に心がけていることは?
この余白をつくるという考えは、仕事でコーディネートをする際も大切にしています。お客様がその後にコーディネートを遊べるようにしているのです。そう、時間とともに皆さんの暮らし方は変化していきますので、インテリアを変えていくことも必要です。もちろん大きな家具や壁紙を変えるのは予算もかかってたいへんですが、ラグやクッションなど小物を変えることは容易で、ぐっと室内の雰囲気を変えることができます。
これまでの経験から、買い替えにくい大きな家具や壁紙は色合いを抑えめにして、小物で雰囲気を変えていく方が、その後の変化に対応しやすくなります。小物を季節ごとに変えて、室内で四季を感じることができるなんてすてきですよね。

神奈川建築コンクール優秀賞を受賞したご自宅のダイニング兼リビング。写真のさらに右手には、中庭に面した大きな窓が開放感を演出
ちょっとした知識で
見え方は大きく変化する
――読者が自宅をコーディネートする際のアドバイスは?
私への依頼としては個人宅の場合、リビングダイニングを変えたいというニーズがもっとも多いでしょうか。リビングダイニングでは、「フォーカルポイント」をつくることが大切です。これは、人の目線が集まる場所をつくること。私の自宅の場合は、壁一面に広がる大きな造り付けの棚です。
たとえば部屋がごちゃごちゃとしているように感じている方は、目線を集めたい1か所を決めて、その他の要素のレイアウトを考えていくようにしてください。その1か所は、壁面に色を入れる、絵を飾る、大きなグリーンを飾るなどさまざまです。
マンションの場合、リビングダイニングが狭いと感じていた方が、コーディネートをした後に「こんなに広かったですか?」といわれることも多々あります。それは、室内に入ったときにフォーカルポイントがあり、「抜け感」もつくったためです。我が家では、ドアを開けると目の前に中庭の見える大きな窓があり、フォーカルポイントである壁の棚まで目線を遮るものを置いていないのです。
テレビの存在も難しいポイントではないでしょうか。映像が流れていないときは、実はただの無機質な黒い塊です。室内に入ったときの目線の先にはソファを置き、テレビは死角となるその反対側にするだけで、雰囲気は大きく変わります。マンションでコンセントなどの配置で制約される場合は、延長コードをうまく使うようにするのがおすすめです。
――アートを飾ることも大切?
アートをインテリアの1つとして飾ることもおすすめしています。アートは、なくても生きていけるものです。でも、心の豊かさにつながるたいせつな存在です。アートというと敷居が高く感じる方もいるかもしれませんが、お子さんの描いたお気に入りの絵をきちんと額に入れて飾るだけでも、当時の思い出もよみがえってきて心が豊かになります。

何かを生み出すためには
体験することが大切
――東武鉄道での旅の経験は?
昨年2月に中禅寺湖のほとりにあるザ・リッツ・カールトン日光に泊まりました。和を意識したホテルの空間や雪景色がすばらしく、東武日光駅の駅舎が山小屋風なことにも驚きました。
そもそも旅が大好きなので、いいホテルも訪ね、インテリアや建築の目線で見ています。SNSなどで写真を見ることはできますが、現場で雰囲気やホスピタリティを感じるようにしているのも私のこだわり。自分が体験したことからしかデザインは生み出せないので、さまざまな体験ができるおでかけは私にとってたいせつです。
WEB限定!
荒井さんが現職になった経緯や
さらなるアドバイスやおでかけへの思い
――インテリアコーディネーターになった経緯は?
私はもともと被服という分野に興味があったこともあって、日本女子大学の被服学科に入学しました。そこで学んだデザイン論の授業は、とても興味を惹かれました。卒業後に設計事務所に入ったのも、やはりデザインに関わる建築やインテリアがおもしろそうと感じてのこと。事務職でしたが、会社では身の回りにデザインやインテリア、建築のさまざまなことがあふれていて、私もこうした分野の仕事にしてみたいと感じました。
すると、たまたま会社のすぐそばに町田ひろ子インテリアコーディネーターアカデミーがあり、会社に勤めながらでしたが入学を決意。自分でつくったものが誰かにに喜んでもらえるという、作り手から発信する新鮮な喜びがありました。
アカデミーを卒業した当時は、まだインターネットもSNSも広まっていない時代。さて、どう活動していけばよいのか……と考え、まずは友人知人にポストカードを送ることにしました。カーテン1枚でも椅子一脚でもいいので、インテリアに関するご相談があれば何なりと知らせてくださいと記して。すると、何々を買いたいのだけれど一緒にきてもらえる?など、うれしいことにいろいろな反響がありました。でも設計事務所に在籍をしていましたので、ランチ代だけいただいくというスタイルでスタート。1年ほどをかけて、インテリアコーディネートに関するパーツパーツの仕事のノウハウを学ぶいい機会を得ることができました。
こした経験を積んだ後、いちばん仲のいい友人が自宅を全面的にリノベーションする際、トータルでコーディネートしてほしいという依頼が入りました。するとこの友人が、「いつまでも無料で引き受けていたらプロではないのでは?」と。確かに!と痛感して、会社を退社してフリーランスになって友人宅を仕事として引き受けました。
さらに、このタイミングで二世帯住宅の自宅を建てることになりました。設計士である夫が設計を担当し、私がインテリアをコーディネートすると役割を分担。この時は、毎週のように現場に足を運び、大工さんと意見を交わすなど、大きな経験となって今に生かされています。うれしいことに、神奈川建築コンクールの優秀賞を受賞することができました。

――インテリアコーディネーターというお仕事の本質とは?
最近のSNSなどを見ていると、上手にコーディネートできている方が多いように感じます。プロの立場として私が常に意識しているのは、お客様がどう暮らしたいか、つまりはどう生きたいかをヒアリングしてコンセプトを固め、実際のインテリアにどう落とし込んでいくかという流れです。コーディネートは部屋に置く物を決める人と見られがちですが、根本となるのは、お客様の生き方に寄り添うこと。具体例をお話ししましょう。
ある夫婦の依頼を受けたとき、お互いに忙しくなかなかコミュニケ―ションが取りにくいようなお話がありました。私の立場で何ができるのか……とじっくりと考えました。
たとえば、食卓はパパっと食事を済ませる場所ではなく、会話が生まれる空間にできないかと考えました。間接照明を当ててレストランやバーのような空間を演出。テーブルも円形のものにして、2人の座る距離が縮まるようにしました。まるでカウンセラーのような役割でしょうか。これからの暮らし方、生き方を聞くことは、もっとも大切にしているポイントです。
――アートなどを飾る際へのアドバイスは?
自宅に飾っている紫の花の写真アートは、講師をしている町田ひろ子アカデミーの教え子たちから卒業式の時にいただきました。好きなアートで見る度に皆さんの顔を浮かんで心が豊かになります。こうしたアートをぜひ、皆さんも自宅に取り入れてみてください。
飾り方もポイントです。小物であれば、私は「三角形の法則」を提供しています。小物を飾る場合、背の高いものと中ぐらいもののと低いものが、三角形を描くように配置すると、とてもバランスがよくなります。ひとつだけだと、ぽつんと寂しい印象で、2つだとシンメトリーな固い雰囲気になり、3つ以上だとごちゃごちゃとしてしまいます。
――よくおでかけする場所は?
日常的に足を運ぶのは美術館やギャラリーです。ジャンルの分け隔たりなく家族でおでかけします。展示作品を鑑賞するのも目的ですが、空間の使い方もとても参考になります。
海外へもよく足を運びます。今年はデンマークで開催された展示会へ、またウィーンやパリへ。旅先でも美術館に行くのが楽しみです。
インフォメーション
荒井さんのノウハウが詰まった著書が好評発売中!
今回のインタビューで教えていただいたインテリアのヒントに加えて、さまざまな荒井さん流のノウハウをまとめた1冊もぜひ、参考にしてみてください。
※サンクチュアリ出版/ Amazonや全国の書店で販売中
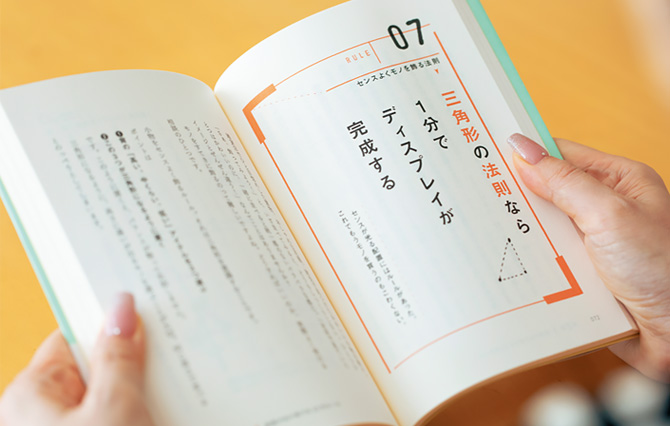
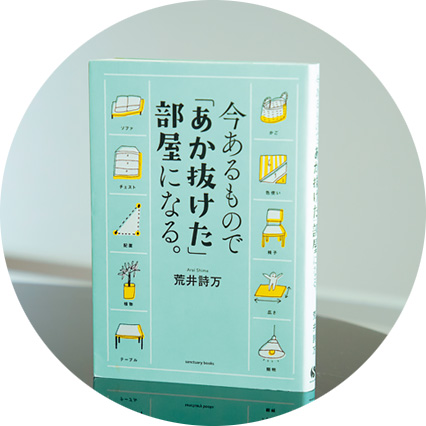
text:Taku Tanji photo:Mayumi Komoto



