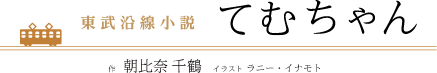-
01
TOP
-
02
あなたのONE SCENE
宝徳寺
-
03
クロストーク
八木莉可子さん
-
04
こよみ、くらし。
中秋の名月
-
05
おとなの私のセルフケア
老い先について考えた話
-
06
ちょっと、そこまで
鎌ケ谷~新鎌ケ谷編
-
07
アートのはなし
-
08
Window on TOBU
-
09
東武沿線小説「てむちゃん」
-
10
てみやげ、おもたせ、心づかい
いま坂どら焼き
-
11
「パズル」でアタマの体操
クロスワード編
-
12
バックナンバー
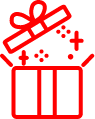 プレゼントがあたる!
プレゼントがあたる!
第10話

今日は私こと払田瑠璃の勤務先、コミュニティセンターが1年で一番賑わう文化祭だ。屋外では、よさこいのチームが軽やかな鳴子の拍子でお客さんの注目を集めている。晴天に恵まれたおかげで、今年もお客さんの入りは良さそうだ。
私は「ミニ押絵羽子板ワークショップ」のブースでポツンと座っているてむちゃんが気になっていた。まだ、お客さんは来ていない様子。
よさこいが終わったと同時に、お客さんが屋内に流れてきた。よし、声かけチャンス! すると、てむちゃんがここぞとばかりに声を張った。
「羽子板、作ってみませんかー!」
「あ、カラリングのてむちゃんだ」
元地域アイドルとしての人気は、地元では健在。けれども、子どもたちは食事ブースへゴー。朝からホットドッグやポテトを揚げる香ばしい油の匂いが屋外にまで漂っているからしょうがない。
「チラシ、見たわよ。よかったわね、てむちゃん、店を継ぐことになったのねえ」
近所の高橋さんだった。親戚のように心配してくれているのは嬉しいけど、その認識は間違いなので正しておく。
「違います。今回は特別なんです」
そうなの?と高橋さんは、怪訝そうな表情をした。
本当は歌を打診されていたけど地域貢献なら押絵羽子板のワークショップをしたい、とてむちゃんから提案したなどと裏事情をばらすわけにもいかない。その場を立ち去ろうとすると、パートの畠山さんが声をかけてきた。
「ワークショップ、呼び込み、苦戦してますね」
「やっぱり、子どもには難しいかな……」
私自身、当時同級生だったてむちゃんと仲良くなるまで、押絵羽子板を見たことも触ったこともなかった。それが親同士の再婚によって今や私も羽子板店の一員だ。
「そんなことないですよ。押絵羽子板、私の地元にはないんですよね。どんなものなのか興味があるんで、手伝ってきていいですか」
どうぞどうぞと促すと、早速、畠山さんはブースに近寄りてむちゃんに挨拶をした。
「ねえ、この子たちも参加していい?」
高橋さんがイキのいいよさこいチームの子らを連れてきた。
「もちろん、もちろん!」
─3名のよさこい衣装姿の小学生がワークショップに加わった。
「羽子板、知ってるよね。家にある?」
てむちゃんの問いかけに、一人が答えた。
「あるけど、何に使うのかわかんない」
「昔は、お正月に羽根つきしたものだけどね……」
高橋さんの子ども時代、羽子板は遊び道具でもあったらしい。
「押絵羽子板で羽根つきは無理ですよね」
畠山さんがそう言うと、てむちゃんが急に前のめりになった。
「そうなんです! 押絵羽子板はお守りとして飾るものなんですよ。ほら、細部まで見てください! 立体的だから一つひとつの表情が豊かでしょう?」
驚いた。いつも家では羽子板のことなど「興味ない」といったそぶりなのに、力説している。
「そもそもこれは、女の子が生まれたときに厄除けの意味で贈られるものなんですよ。歌舞伎の襲名披露にも贈られたりして、縁起物でもあるんです」
熱のこもった説明は、まるで展示会のときのママのよう。
「さあ、地元の伝統工芸品で、世界に一つだけの自分のお守りを作ってみよう!」
てむちゃんが子どもたちに呼びかけると、
「自分だけのお守り!?」とみんな興味津々の表情になった。
まずは顔などのパーツ毎の型紙に合わせて布を裁断する。裁断した布と木板との間に入れる綿の塩梅が難しい。でも、てむちゃんは細やかに手が動く。さすが日頃から手伝っているだけある。
「手際いいわね。そのうち店を継ぐことになるわよ」
高橋さんの独り言を、私は聞いていないふりをした。
「継がないわよ」
聞き慣れた低い声が聞こえてくると思ったら、腕を組んだママがいた。
「あの子、裏方タイプじゃないもの」
すると、ママはてむちゃんに近づき、テキパキと指導し始めた。
「やっぱり母娘よね。いろいろ、そっくりだわ」
高橋さんの含みのある呟きに、私も思わずうなずいてしまった。
著者プロフィール
文筆家、脚本家。2021年日本シナリオ作家協会主催「新人シナリオコンクール」佳作受賞。現在は、小説執筆のほか、脚本家としてテレビや映画の仕事に携わる。